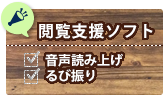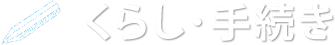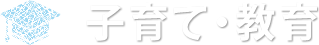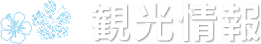経営所得安定対策等の概要
更新日:2026年01月05日
経営所得安定対策では、担い手農家の経営の安定に資するよう、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正する交付金(ゲタ対策)と、農業者の拠出を前提とした農業経営のセーフティネット対策(ナラシ対策)を実施しています。
また、令和元年からは、全ての農産物を対象に収入減少を広く補償する収入保険制度も実施しています。
さらに、食料自給率・食料自給力の維持向上を図るため、飼料用米、麦、大豆など戦略作物の本作化とともに、地域の特色を活かした魅力的な産地づくり、高収益作物の導入・定着等を進め、水田のフル活用を図る水田活用の直接支払交付金を実施しています。
水田活用の直接支払交付金
水田で食料自給率・自給力の向上に資する麦、大豆、飼料作物等の作物や高収益作物を生産する農業者に対して交付金を直接交付することにより支援します。
交付対象者
水田を活用して販売目的で対象作物を生産する販売農家・集落営農組織
支援内容
1.戦略作物助成
| 対象作物 | 交付単価 |
| 麦、大豆、飼料作物 | 35,000円/10a |
| WCS稲 | 80 ,000円/10a |
| 加工用米 | 20,000円/10a |
| 飼料用米、米粉用米 | 収量に応じ、55,000円~105,000円/10a |
※基幹作のみ対象
※飼料作物は、飼料用とうもろこしを含む
※多年草牧草について、当年産において播種を行わず収穫のみを行う年は10,000円/10aで支援
※飼料用米、米粉用米について、過去実績から標準単収以上の収穫が確実だったと認められる者には、自然災害等の場合でも、特例措置として標準単価(80,000円/10a)で支援
2.産地交付金
白浜町地域農業再生協議会で作成する「水田収益力強化ビジョン」に基づき、地域の特色を活かした魅力的な産地づくりに向けた取組を支援します。
国から配分された資金枠の範囲内で、和歌山県と白浜町地域農業再生協議会が助成内容(交付対象作物・取組・単価等)を設定しています。
| 取組内容 | 対象作物等 | 交付単価 |
| 高収益作物 | 販売野菜、果樹、花き | 16,000円/10a |
| 地域振興作物 | 未成熟とうもろこし、しそ、球状レタス、うすいえんどう | +35,000円/10a |
| 地域振興作物の作付拡大支援 | 前年と比較して栽培面積の増加面積分 | +12,000円/10a |
※令和7年度産の単価予定になります。交付単価は、変更することがあります。
3.申請手続きのスケジュール
| 内 容 | 提出期限等 | 提出書類等 |
| 申請受付 | 6月末 |
1.経営所得安定対策交付金交付申請書 2.経営所得安定対策交付金振込口座届出書、振込先通帳の写し ※新規申請の方、振込口座を変更したい方 3.水稲共済細目書異動申告票(一体化様式) |
| 実績報告 | 11月末 |
1.実績報告書兼誓約書 2.販売伝票等の写し ※対象作物毎に必要 |
※出荷・販売契約書、販売伝票等、種子や苗の購入伝票、作業日誌等については、5年間保管しておいてください。
※営農計画書(細目書)に記載された計画により対象作物の作付確認を行います。変更がある場合は、速やかに報告をお願いします。
水田活用の直接支払交付金における5年水張りルールの見直しについて
令和4年度から8年度までの5年間で一度も水張り(水稲作付)が行われていない水田については、令和9年度以降、交付対象水田から除外されることとされてきましたが、令和7年4月の見直しにより、令和9年度から水田を対象として支援する水田活用の直接支払交付金を、作物ごとの生産性向上等への支援へと転換することとなりました。
このため、令和9年度以降、「5年水張り要件」は求められなくなりました。
また、現行水活の令和7年度、8年度の対応として、水稲を作付け可能な田について連作障害を回避する取組を行った場合、水張しなくても、交付対象とすることとなりました。
今までの5年水張りルール
令和4~8年度の間に、
・水稲作付または
・1か月以上の灌水管理(かつ、連作障害による収量低下等の発生が確認されていないこと。)
変更後の5年水張りルール
令和4年度から8年度の間に、
・水稲作付または
・1か月以上の灌水管理または
・連作障害を回避する取組(令和7年度または8年度)
※令和4~6年度に、水稲作付または1か月以上の灌水管理に取り組んだほ場は、令和7年度または8年度の連作障害回避の取組は必須ではありません。
※1か月以上の灌水管理を実施した場合、連作障害による収量低下等が発生していないことの確認は求めないこととします。
連作障害を回避する取組とは
・土壌改良剤、有機物(堆肥、もみ殻等を含む)の施用
・土壌に係る薬剤の散布
・後作緑肥の作付け
・病害虫抵抗性品種の作付け
・その他地域農業再生協議会等が連作障害を回避する取組であると判断する取組
例えば・・・
・最適な土壌pHに矯正するため、播種前に苦土石灰を施用
・土づくりに向け、播種前に、発酵鶏糞を施用
・センチュウ対策として、作付前に、くん蒸型の薬剤を使用し、土壌消毒 など
連作障害回避の取組の確認方法について
「連作障害を回避する取組」を行ったことの根拠資料として、
・取組を講じたことが分かる書類(作業日誌、栽培管理記録簿等)や
・当該作業に用いた資材の入手状況が分かる資料(購入伝票等)
を補完し、白浜町地域農業再生協議会の求めに応じて提出できるようにしておいてください。